
波止の3大釣法といえば…
探り釣り、ウキ釣り、投げ釣りです。中でも探り釣りは、その名の通り竿一本シンプルな仕掛けで探って歩く、釣りの基本形とも云えるものです。手にピクピクと来るアタリに釣りの醍醐味があります。
探り釣りってなに?
 探り釣りとは読んで字のごとく、魚を求めて探って歩く釣りをいいます。ウキ釣りや投げ釣りのように、仕掛けを流したり飛ばしたりしませんから、釣り方も仕掛けもシンプルです。ですから仕掛け作りの苦手な初心者にも向いています。ウキを介したりしませんから、アタリはダイレクトに体感できます。シンプルながらも極めて釣果が期待でき、魚の魚信を身体で感じる快感故に、長年これ一本というベテランもいます。
探り釣りとは読んで字のごとく、魚を求めて探って歩く釣りをいいます。ウキ釣りや投げ釣りのように、仕掛けを流したり飛ばしたりしませんから、釣り方も仕掛けもシンプルです。ですから仕掛け作りの苦手な初心者にも向いています。ウキを介したりしませんから、アタリはダイレクトに体感できます。シンプルながらも極めて釣果が期待でき、魚の魚信を身体で感じる快感故に、長年これ一本というベテランもいます。
探り釣りには色々なバージョン、あるいは地方によって、それぞれ呼び方があります。覚えておくと便利ですから、紹介しましょう。
ミャク釣り
魚のアタリを脈を計るようにとることから、名付けられた別名です。
フカセ釣り
鈎のみ、あるいは小さなジンタンオモリを付けただけという仕掛けは、海の中でハリスが流れでたなびき、エサがナチュラルな動きをするので、喰いがよいとされています。たなびくように糸をふかせて釣るので、フカセ釣りといいます。探り釣りのバージョンの一つですが、磯釣りでも軽いウキ仕掛けをフカセ釣りといいますので、混用しないように。
際づり
波止や護岸の際は魚の住処になっていて有望なポイントの一つです。際を狙って釣りますから際づりといいます。探る場所を際に特化した釣り方です。大阪湾では、竿をこするように探って行きますので、コスリ釣りとも呼ばれています。
ヘチ釣り
関東ではこの際のことをヘチといいます。際釣りの別名ですが、関東では特に短竿で、黒鯛やアイナメを狙う特化型の釣りのことを、こう呼びます。
落とし込み釣り
特に黒鯛専用に開発された釣りです。軽い仕掛けをゆっくり上から落とし込んで釣る釣りです。手でアタリをとるときもありますが、現在では小さな目印や、糸ふけの変化でアタリをとる専門化された釣りに変化しています。目印を使った仕掛けの発祥は名古屋とされています。
前打ち
これも黒鯛のための釣法で、同じく中京方面が発祥とされています。際を攻めるだけでなく、より長い竿を駆使して、沖も攻めるというコンセプトの探り釣りです。
穴釣り
際狙いでなく、テトラの穴に潜む根魚を専門に狙う探り釣りバージョンです。非常に効果的な釣り方で、初心者にも間違いなくお土産が期待できます。短竿を用います。
基本仕掛け
竿選びのポイント
 防波堤の高さで選びます。一概に云えませんが関西方面の高い波止なら3.6~5.3mの長目、関東の低い波止なら短めの2.1~3.6mを選びましょう。長短使い分けるズーム式も便利。沖やテトラの先を攻めるなら、5mは必要です。
防波堤の高さで選びます。一概に云えませんが関西方面の高い波止なら3.6~5.3mの長目、関東の低い波止なら短めの2.1~3.6mを選びましょう。長短使い分けるズーム式も便利。沖やテトラの先を攻めるなら、5mは必要です。- ガイドが小さく先調子のズーム式落とし込み竿が使いやすいです。長さは店員さんと相談して下さい。竿さばきに慣れないうちは、固めの筏竿2.1m程度も面白い釣りができます。商品数は少ないですが、ヘチ専用竿が入手できれば最高。
対象魚 チヌ・メバル・スズキ・カサゴ・アイナメ・アコウ・ハゼなど

リール選びのポイント
 落とし込み専用の太鼓リールが面白いですが、初心者ならば道糸2号100m程度が巻ける小型の両軸リールの方が扱いやすいです。
落とし込み専用の太鼓リールが面白いですが、初心者ならば道糸2号100m程度が巻ける小型の両軸リールの方が扱いやすいです。- スピニングリールはこの手の釣りには向いていません。馴れればわかります。
小物選びのポイント
- 基本的には水深と穂先の固さにあわせて選びます。
- 丸玉オモリ0.5号/1号/2号ぐらい
- ガン玉/2G・B・3B・5B程度 ※ケース入りのセットものがあります。
- サルカンは超小型サイズで充分。
- カニエサにはカニ専用落とし込み鈎を使う
探り釣りのツボ
シンプルですから誰にでも挑戦できます。比較的魚影の薄い釣り場でも、お土産が期待できる美味しい釣り方です。凝らないかぎり、道具やエサに掛かる費用も安上がりです。
狙える魚
関西~関東の一般の波止なら、メバル・アイナメ・カサゴの根魚御三家に加え、チヌ、スズキといったところでしょう。いずれも美味しい魚が釣れるのが魅力です。
初心者の場合の釣り方
フカセ釣りのような繊細な仕掛けで、アタリをとるのは難しいでしょう。初めのうちは穂先が少し曲がるくらいのオモリ(0.5~2号)を掛け、糸がピンと張る状態で探っていきましょう。馴れれば徐々に軽いオモリに替えていきます。その方がチヌやメバルのアタリが出やすくなります。テトラの穴釣りのような場合は、波気でもまれて仕掛けが落ち着かない場合があります。そんな時は軽い仕掛けにこだわらず、どっしりしたオモリ(2~5号)を使いましょう。
仕掛けの落とし方
メバルやチヌのように、遊泳層が上から下まで変化する魚は、仕掛けを上から落としていくのが基本です。すとんと落とさずゆっくり落としましょう。アイナメやカサゴのように底にべったり居る魚の場合は、重めのオモリで一気に落としてかまいません。底に着いたらしばらく待ち、ゆっくり引き上げていきます。いずれの場合も、魚が鈎に掛かれば、アタリが穂先か、手元にしっかり伝わりますので、まず魚信を見逃すことはありません。アタリが出れば竿を立て、魚を取り込みましょう。
釣果にありつく秘訣
探り釣りは歩いて稼ぐ釣りです。荷物を少なくまとめ軽装で、端から端まで歩いて探っていきましょう。アタリが出なければすぐ3~5m移動してもかまいません。狙いのポイントはコンクリートの継ぎ目、前打ちならテトラや、護岸の捨て石の入っている切れ目です。
2019/11更新

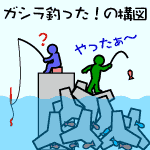

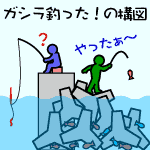 防波堤の高さで選びます。一概に云えませんが関西方面の高い波止なら3.6~5.3mの長目、関東の低い波止なら短めの2.1~3.6mを選びましょう。長短使い分けるズーム式も便利。沖やテトラの先を攻めるなら、5mは必要です。
防波堤の高さで選びます。一概に云えませんが関西方面の高い波止なら3.6~5.3mの長目、関東の低い波止なら短めの2.1~3.6mを選びましょう。長短使い分けるズーム式も便利。沖やテトラの先を攻めるなら、5mは必要です。 落とし込み専用の太鼓リールが面白いですが、初心者ならば道糸2号100m程度が巻ける小型の両軸リールの方が扱いやすいです。
落とし込み専用の太鼓リールが面白いですが、初心者ならば道糸2号100m程度が巻ける小型の両軸リールの方が扱いやすいです。